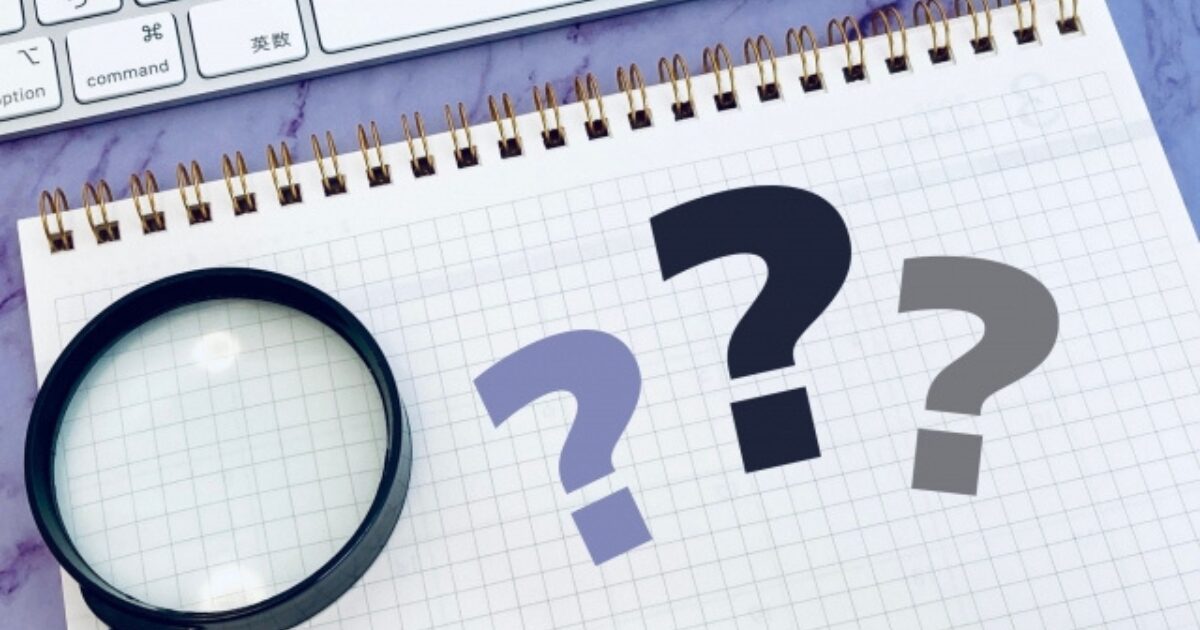こんちわっす!
いきなりですが
「柔道整復師と理学療法士」
違いをはっきり言えますか?
おそらく大半の人が答えられないと思います。
そらぁそうですよね。
医療従事者の人でも完璧に答えられる人は少ないと思います。
そもそも「柔道整復師と理学療法士」自体を知らない人も居るでしょうでしね(笑)
超簡潔に結論を言うと
柔道整復師・・・怪我の治療を行う専門家
理学療法士・・・リハビリの専門家
といった所でしょうか。
ちょっとざっくりし過ぎましたかね💦
では詳しく見ていきましょう!
柔道整復師と理学療法士の共通点
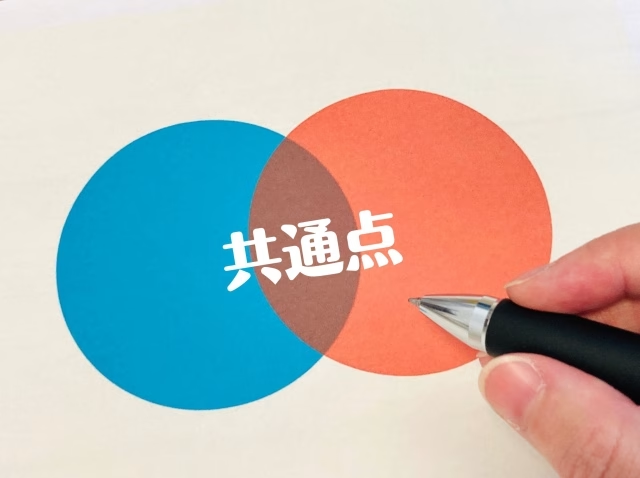
柔道整復師と理学療法士の専門性には違いがありますが、医療従事者といった面では共通点がいくつかあります。
①医療系の国家資格である
②資格取得には養成学校に通う必要がある
③基礎的な知識は同じ
④活躍の場が似通っている
①医療系の国家資格である
共通点の1つ目として、医療系の国家資格であるという点です。
大きな括りで見ると同じ医療職になります。
この辺りは一般の方でもイメージがしやすいと思います。
②資格取得には養成学校に通う必要がある
2つ目は資格取得には養成学校に通う必要がある点。
専門学校や大学に通って国から定められたカリキュラムを履修しなければなりません。
さらに、カリキュラムを履修した上で国家試験に合格する必要があります。
通信制などでの資格取得は不可です。
③基礎的な知識は同じ
3つ目は基礎的な知識は同じという点。
これは柔道整復師と理学療法士に限った事ではありません。
その他の医療従事者にも当てはまる事です。
- 解剖学
- 生理学
- 運動学
- 病理学
- 一般臨床医学
- リハビリテーション医学
- 公衆衛生学
医療に携わる上での基礎的な部分になります。
基礎科目を履修してから各々の専門科目を学んでいくといった流れになります。
基礎が出来ていないと専門分野の理解も難しくなるので重要な部分ですね!
”何事も基礎が大事”
ですから☺
④活躍の場が似通っている
4つ目は活躍の場が似通っているという点。
柔道整復師も理学療法士も基本的には医療の現場で働く事が多い職業です。
臨床現場から求められるニーズは高いですね。
主な活躍先は以下の通りです👇
- 介護福祉施設
- 病院や整形外科
- スポーツ現場
- 一般企業
一般企業というとあまりイメージが沸かないと思いますが
スポーツメーカーや医療・福祉器具メーカー
で働くという選択肢もあります。
解剖学や運動学の知識が製品の開発や営業などに活かせるという強みがあります。
インソール専門店の営業販売をしている柔道整復師の友人も居るくらいです。
働き方が多様化して色々な分野で活躍できる可能性が高まっている証拠ですね♪
柔道整復師と理学療法士の違い
では共通点が分かった所でそれぞれの違いについて見ていきましょう!
①専門科目の違い
まずは専門科目の違いからです。
- 柔道整復理論
- 関係法規
- 外科学
- 理学療法
- 臨床医学大要
- 臨床心理学
共通科目とは違い、それぞれの特色が顕著に出ています。
柔道整復師の専門科目

柔道整復師は怪我や外傷の知識に特化している部分が特徴的です。
従って、履修科目や国家試験の出題範囲の大部分を柔道整復理論が占めます。
柔道整復理論では骨折・脱臼・捻挫などに対しての整復法や固定技術を主に学びます。
これについては読んで字の如くですね。
詳しくはこちらから👇
その他には関係法規など、聞き慣れない学問もカリキュラムとして取り入れられています。
「関係法規って何?」
って感じですよね?
簡単に言ってしまえば
【柔道整復師業界の法律】※正式には柔道整復師法
と言った所ですかね。
- 柔道整復師に相応しい人物か
- 免許申請や交付についての決まり事
- 施術所を開設する際の必要書類
- 施術所の構造基準の取り決め
- 柔道整復師業務の禁忌事項
- 個人情報の取り扱いや広告制限の遵守
難しい言葉で書いていますが主な内容を要約するとこんな感じになります👆
基本的なルールを定めた説明書の様な感じですね💡
理学療法士の専門科目

理学療法士はリハビリに特化した資格です。
中でも「臨床医学大要」という科目が特徴的です。リハビリに必要な医学的知識から対象者の心理状態の把握などを含めた総合的な科目になります。
また、理学療法士は身体評価を行うスペシャリストでもあります。
- 筋力
- 関節可動域
- 運動麻痺の程度
- 平衡感覚
- 日常動作能力(ADL能力)
- 認知機能
評価に基づき
リハビリプログラムの計画作成 ⇒ 実施 ⇒ 評価
のサイクルを定期的に行います。
科目でいう所の「理学療法」に当たる部分です。
臨床実習では徹底的にこの技術を身に付けます。
長ければ2ヵ月間に及ぶ実習もあります。
これは柔道整復師には無い専門性ですね。
凄い!羨ましい!!
②国家試験合格基準の違い
続いては国家試験合格基準の違いをどうぞ。
・必修問題 50問(80%以上) ⇒ 40点以上
・一般問題 200問(60%以上) ⇒ 120点以上
※両方の基準点を満たす事が条件(1問1点)
・一般問題 160問 ⇒ 160点満点(1問1点)
・実地問題 40問 ⇒ 120点満点(1問3点)
※総得点の60%以上(168点以上)かつ実地問題の35%以上(43点以上)を満たす事が条件
理学療法士の合格基準が少し複雑ですが
どちらの資格も2つの分野で合格基準を満たす必要があります。
柔道整復師の合格基準については令和元年度に一部改訂がありました。
改訂内容はこちらから👇
この改定により合格率にやや変動がありました。
合格率については次項で説明します。
③国家試験合格率と人数の違い
最後は国家試験合格率と人数の違いです。
・合格率 約50%~66%(2020~2024年)
・人数 約7万8千人(2022年12月時点)
・合格率 約79~89%(2020~2024年)
・人数 約21万3千人(2023年3月時点)
データを見比べてみると
❶合格率は理学療法士の方が高い
❷理学療法士の人数は柔道整復師の約3倍
という事が分かります。
では2つの資格に
「何故これほど差が出るのか?」
について解説していきます。
合格率に違いが出る理由

合格率を指しはかる上で重要な項目があります。
【新卒者】と【既卒者】という概念です。
両者を比べてみると新卒者の方が圧倒的に合格率が高い傾向にあります。
既卒者を分かりやすく言ってしまえば
「浪人生」
という事になります。
大学受験を想像してみて下さい。
浪人生より現役高校生の方が合格しやすいというイメージはつきやすいですよね?
国家試験も同様です。
既卒者が多ければ全体的な合格率は必然的に下がってしまいます。
どちらかと言うと柔道整復師の方がこの傾向が強い状況にあります。
「合格基準の改訂」
により合格率が低下した事なども影響している可能性があります。
人数に違いが出る理由

柔道整復師と理学療法士の人数の差に違いが出る理由は主に2つあります。
❶養成学校数の違い
❷必要とされる分野の違い
まず1つ目は養成学校数の違いです。
令和7年現在、柔道整復師養成学校は減少傾向・理学療法士養成学校は増加傾向にあります。
そもそもの学校数が違えば人数に差が生まれてくるのは当然の事ですよね。
2つ目が必要とされる分野の違いです。
これは活躍するフィールドが主に違う事が要因になっています。
| 主な活躍の場 | 対象者の特徴 | |
| 柔道整復師 | 整骨院 | 子供~高齢者 |
| 理学療法士 | 病院や介護施設 | 中壮年~高齢者 |
現在、日本は超高齢化社会を迎えています。
今後も高齢者の割合が増える事が予想される為、病院や介護施設で専門性を発揮できる理学療法士の需要が高まっています。
これは前述した養成学校が増えている理由の1つにもあたります。
柔道整復師の需要も高まっていますが、それ以上に理学療法士への期待が高まっているという証拠ですね💡
④開業権の有無

最後と言いつつもう1つありました(笑)
これはけっこう大きな違いになります!
「開業権の有無」
です。
医療分野でいう開業権の定義とは
“保険診療が法律上で認められている”
という事になります。
結論から言うと
柔道整復師は認められており、理学療法士は認められていません。
医療系の国家資格で保険診療を認められているのは
【柔道整復師と医師】
のみになります。
これは意外に思った方も多いのでは?
柔道整復師の場合は
”受領委任制度”
と呼ばれます。
呼び方は違いますが柔道整復師も医師も健康保険を使って診療する事には変わりはありません。
柔道整復師の魅力の1つとして挙げられるのがこの受領委任制度です。
- 健康保険を使えるので患者の負担が少ない
- 国から認められている制度なので安心感がある
- 安定的な売上が見込める
やはり最大のメリットは患者の負担額が少なくて済むという点ですね。
負担額が少ないという事は治療に通いやすくなり、通院頻度を気にしなくても良くなります。
負担額の上限は基本的には3割です。
よほどの高額な治療費でなければ、最低限の負担で治療を受けれるので庶民の心強い味方です☺
また、国家資格者である柔道整復師や医師から治療を受けれる事も安心感がありますよね!
整骨院側からすると安定的な売上が見込める点もメリットです♪
受領委任制度についてはこちらでも軽く触れています👆
一方で理学療法士には開業権が認められていません。
じゃあ泣き寝入りするしかないのか・・・
そんな事はありません!
理学療法士でも治療院を開業をする方法はあります。
その方法は
自由診療での開業
です!
健康保険を使えないというデメリットはありますが
やり方次第では他院との差別化も図れると思います。
余談ですが
養成学校時代のクラスの人に理学療法士の方がいました。
「理学療法士では開業が出来ないから柔道整復師を取りに来た」
凄い猛者もいたもんです(笑)
柔道整復師と理学療法士の良いところ取り、最強過ぎます😲
まとめ
長々と両資格の違いについて考察してきましたが、まとめると下記になります。
| 専門性の違い | 活躍の場 | 合格基準 | 合格率 | 人数 | 開業権の有無 | |
| 柔道整復師 | 怪我の治療に特化 | 整骨院 | 必修問題40点以上 一般問題120点以上 | 約50~65% | 約8万人 | 〇 |
| 理学療法士 | リハビリに特化 | 病院・介護施設 | 総得点の60%以上かつ実地問題35%以上 | 約80~90% | 約21万人 | × |
それぞれに特色や独自の専門性がある為、一概にどちらが良いかという議論はナンセンスです💦
柔道整復師や理学療法士などの医療分野に興味のある方、そうでない方も。
この記事を読む事で皆さんの人生が明るいものになれば嬉しいです!(^^)!
ではまた♪